こんにちは しさブロ管理人加納です
今回は橘玲さんの「貧乏はお金持ち」について解説します
橘玲さんは様々な本を出版されていますが、特にこの本は私がブログを始めたきっかけになります
来年から就職する私に対して素晴らしい問題提起をしてくれた素晴らしい本なので是非読んでください
1.なぜ「新・貧乏はお金持ち」なのか?
──国家に搾取される構造から脱却せよ──
「貧乏は自己責任」ではない日本の真実
橘玲氏が一貫して主張しているのは、「日本における貧困とは、個人の努力不足ではなく、制度的に構造化された搾取の結果である」という視点です。本書の序盤では、これを明快に表すキーワードが登場します。それが「国民負担率:46.2%」という数値です。
これは、私たちが稼いだお金のうち、約半分が税金や社会保険料として国に吸い上げられているという事実を示しています。
しかも、目に見える「所得税」だけでなく、「住民税」「厚生年金」「健康保険料」など強制的に天引きされる公的負担すべてを含めた数字です。
江戸時代より重い?「近代の年貢制度」
本書では、現代のサラリーマンを江戸時代の農民に例える大胆な視点が登場します。
江戸期の農民は、収穫の4〜5割を「年貢」として領主に納めていました。現代の日本のサラリーマンも、収入の半分近くを「国家という領主」に吸い取られているのです。
しかも、江戸時代と違って今の私たちは、国から住む土地ももらえなければ、生活保障も十分ではありません。
年金制度は破綻寸前、医療負担は上昇、物価は上がるのに給与は上がらない。
つまり、近代の方がむしろ“支配されている度合いが深刻”であると、橘氏は指摘しています。
日本型雇用の崩壊と、インフレによる実質貧困化
もう一つ本書で問題視されているのが、「日本型の正社員制度がもはや機能していない」という点です。
- 終身雇用は幻想化
- 年功序列賃金は停滞
- 昇進・昇給の可能性は一部の勝者のもの
さらに、2020年代に入りコロナショックや世界的インフレが続いているにもかかわらず、日本の名目賃金はほとんど上がっていません。
少しずつ上がっているという報道もありますが、インフレ率に追いつかないため、実質賃金は下がり続けているのが現実です。
たとえば:
- 物価上昇率:+3〜4%
- 賃金上昇率:+1〜2%(一部業種のみ)
- → 実質的な購買力は減少
増税メガネと「ステルス増税」の正体
政治的な背景としても「増税メガネ(岸田首相)」という揶揄があったように、政府は明確な増税を避けつつ、社会保険料の引き上げなど“バレにくい増税”で国民を追い詰めていると、本書では強く批判されています。
- 消費税は据え置きでも…
- 厚生年金・健康保険料は年々じわじわ増加
- しかも「会社が半分負担しているから見えにくい」=ステルス増税
国民の多くは給料明細を見て、「基本給は上がっているのに、手取りが減っている」という矛盾を感じ始めているはずです。その正体こそが、社会保険料・控除・課税のトリプルパンチなのです。
「頑張っても報われない」構造的な絶望
このように、本書が伝える1章の最大のポイントは:
「いま日本で“普通に”働いている限り、貧困から抜け出すことは極めて難しい」
という冷徹な現実です。
- 労働時間を増やしても手取りは減る
- 子どもの教育費や住宅ローンで生活は火の車
- 老後は年金不安と医療負担がのしかかる
つまり、サラリーマンという雇用形態では、「搾取される側」から抜け出せないのが現代日本の姿なのです。
だからこそ“マイクロ法人”が救いになる
この1章のまとめで、橘氏が読者に投げかけるのは以下の問いです:
「あなたはまだ“雇われることが安全”だと信じていますか?」
答えは明白です。「国民負担率46.2%」という数字が、いまの制度がいかに歪んでいるかを雄弁に語っているのです。
だからこそ、雇われる側から雇うつまり法人の立場になることが必要であり、その第一歩が「マイクロ法人」の設立なのです。
2.マイクロ法人を作れば確実に金持ちになれる理由
──なぜ金持ちは全員マイクロ法人を使っているのか?──
マイクロ法人とは?個人と法人の“二刀流モデル”
「マイクロ法人」とは簡単にいえば、自分一人だけ、もしくは家族だけで運営する超小規模な法人(会社)のことを指します。
- 取締役=自分
- 従業員=いない(もしくは家族)
- 売上の大半=自分の個人活動から発生
この仕組みの肝は、個人と法人を別人格として扱えることです。
つまり、法人で利益を出しつつ、個人の手取りを最適化するという“節税の最強構造”を合法的に作り出せます。
実質税率が激減!手取りが最大化される仕組み
年収300万円のケースで比較
| 区分 | サラリーマン | マイクロ法人活用 |
|---|---|---|
| 所得税+住民税 | 約20%(約60万円) | 法人税18.5%(約55万円)+経費化可 |
| 社会保険料 | 約90万円 | 役員報酬を下げればほぼ0も可能 |
| 手取り額 | 約150万円 | 最大240万円〜可能 |
同じ300万円を稼いでも、マイクロ法人を通すだけで手取りが+90万円近く変わる可能性があります。これは年収を倍に増やすよりもはるかに簡単で、効率的です。
マイクロ法人の実践ステップと構成モデル
基本構成:
- 個人事業主(または副業的活動)として稼ぐ
例:YouTube収益、ライター、アフィリエイト、フリーランス報酬など - 法人を設立し、売上の一部または全部を法人に移す
法人→代表(自分)への報酬を調整=所得をコントロール - 法人側で経費計上を最大化し、利益(課税対象)を圧縮
設立のハードルは?
- 登記費用:約15万円(合同会社なら)
- 税理士依頼(希望者):月1万円前後
- 法人口座・印鑑など:ネットサービスで完結可能
- 法人維持コスト:年間7万円程度(赤字でも)
年収300万円を超える人なら「ペイ可能」かつ「メリットが上回る」ケースが大半
マイクロ法人の節税・節保険スキーム一覧
① 経費化による課税所得の圧縮
法人では下記すべてが経費対象にできます:
- パソコン・スマホ
- 自宅家賃の一部(事務所使用分)
- 書籍・教材・新聞
- 交通費・通信費
- 家族への役員報酬(後述)
個人では経費にできないものも、法人なら“堂々と合法”で経費にできる
② 役員報酬を0円〜に調整し、保険料・税負担を激減
マイクロ法人の設計上、自分への給与(=役員報酬)を自由に設定可能です。
- たとえば年収96万円未満に設定すれば所得税・住民税・国保料も最小に
- 所得がほぼゼロなら、社会保険の加入義務もないため、保険料は0円に
これにより、法人は利益を残さないようにしつつ、個人の所得も最低限で設計することで、“ダブルで節税”が可能になります。
③ 家族も役員にして節税チームを構築
- 専業主婦の妻を役員に → 年96万円まで無税で報酬支給(しかも経費化)
- 子供が大学生なら → バイト代代わりに役員報酬で支払う(教育費も実質経費化)
所得分散+経費計上+税金ゼロ化が同時にできる、究極の節税チームが構築可能です。
法人ならではの“魔法の出張日当”制度
法人ならではの裏技に「出張日当規定」という制度があります。
- 出張費は領収書不要・定額で経費化OK(1日5,000円〜1万円が相場)
- 家族と旅行しながらも、名目上“出張”にすることで経費化可能
- 国家公務員も同制度で“日当”を受け取っているため合法性も安心
つまり、実際の支出がなくても、合法的に経費化できる抜け道があるということ。
重要:これは“税逃れ”ではなく、“制度を知っている人だけが使える知恵”
本書が強調するのは、この仕組みはすべて合法であり、特権階級(官僚・経営者)は当たり前のように使っているという事実です。
- 財務省も出張日当制度を用い、
- 上場企業の経営者も所得を法人に付け替えて節税している
「庶民がやるとズルいと思われるが、上級国民は当然のようにやっている」
→ だからこそ、私たち庶民も知識武装して使うべきだと本書は強く訴えます。
まとめ:マイクロ法人は「知っている人だけが得をする、最強の生活防衛術」
| メリット項目 | マイクロ法人活用の効果 |
|---|---|
| 税金 | 個人所得税(最大45%)→ 法人税18.5%へ圧縮 |
| 社会保険料 | 役員報酬を下げればゼロも可能 |
| 経費 | 家賃・光熱費・書籍・交通費なども経費化 |
| 家族報酬 | 96万円以下で無税支給かつ経費計上OK |
| 出張費(日当) | 領収書不要で旅行も経費扱いに |
3.金持ちだけが知っている制度の抜け道とは?
──制度を知らない者から国は吸い取る──
なぜ「損する人」と「得する人」に分かれるのか?
本書『新・貧乏はお金持ち』の第三章では、こう問いかけられます:
「サラリーマンはなぜどれだけ働いても豊かになれないのか? 逆に、自営業者や経営者はなぜ“自由にお金を使える”のか?」
答えは極めてシンプルです。
同じ年収でも、支払う税金と保険料がまるで違うから。
そしてこの差は、制度を“知っているか、知らないか”だけで決まるのです。
国は“知ってる人”には優しい制度を用意している
著者・橘玲は、日本の社会制度を「知識のある者を優遇し、無知な者を静かに搾取する仕組み」と喝破します。とくに、次のような階層構造が浮き彫りになります。
| 層 | 扱われ方 | 制度活用例 |
|---|---|---|
| 上級国民 | 制度設計の主導層 | マイクロ法人/資産分散/役員日当 |
| 中流〜庶民 | まじめに納税・保険料天引き | 会社員/年金・健康保険フル負担 |
| 無知な層 | 黙って吸い取られる | 手取り減・生活費圧迫 |
具体例①:年金制度の構造的「逆再分配」
▼ 赤字の国民年金をサラリーマンが支えている⁉
- 自営業者:国民年金(月17,000円前後)
- サラリーマン:厚生年金(給料連動/自己負担月45,000円〜)
→ 実はこの2つの制度、“共通の基礎年金”で結びついているため、自営業者が払った分以上の年金をもらえるよう、サラリーマンが差額を穴埋めしています。
つまり、あなたの厚生年金は、自営業者の老後資金に流れているというわけです。
具体例②:健康保険の「払う人」と「得する人」
- サラリーマン:組合健保/協会けんぽ → 給料比例で保険料上昇
- 自営業者:国民健康保険 → 所得に応じて負担を圧縮可能
しかも、健康保険の給付内容は所得に関係ない。つまり…
- 保険料90万円払ってる人も
- 20万円しか払ってない人も
→ 同じ治療・同じ病院・同じ保険証で医療を受けられる。
結論:払う額が少ない人ほど得をしている制度。
ではなぜサラリーマンだけが「損」なのか?
答えは簡単です:
会社に属しているから、強制的に高額の社会保険料・税を徴収されてしまう。
- 天引きのため「支払っている実感が薄い」
- 本人の意思で調整できない
- 控除・節税手段が極端に限られている
これはいわば「制度に従順な者ほど損をする」構造といえます。
しかし、金持ちはこの“制度の裏”を知っている
多くの金持ち(特に中小企業オーナーや士業・資産家)は、以下のような戦略で「制度の穴」を活用しています。
所得を“個人”ではなく“法人”にする
→ 税率が下がり、経費計上も自由に。保険料も最小に。
家族を法人に登用して「合法所得分散」
→ 妻や子に年96万円以下で報酬 → 無課税・かつ法人の経費。
出張・接待・自宅利用などすべて経費で処理
→ マイカーも、ガジェットも、オフィスも、“ビジネス利用”で経費化。
青色申告よりマイクロ法人が優れている理由
一見、青色申告(個人事業主)でも同じに見えるが…
| 項目 | 青色申告(個人) | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 所得税 | 個人課税(〜45%) | 法人税(最大18.5%) |
| 家族への報酬経費化 | 原則不可(控除制限) | 役員報酬で全額経費可能 |
| 社会保険の加入義務 | 任意 | 年収調整で免除可能 |
| 出張日当の運用 | なし | 規定を設ければ支給可 |
「制度の穴」に入れる自由度の高さがまるで違います。
典型的な“裏技”実例:家族旅行が経費になる
法人が「出張日当規定」を導入すれば…
- 夫婦で旅行=“役員出張”に設定
- 1日3万円(2人分で6万円)を出張日当として支給
- 宿泊費・交通費+日当→すべて経費処理
この制度は、国家公務員でも同じように運用されています(実際に課長クラスで日当2万円以上)。
つまり、税務署が咎められない=完全合法スキームです。
国も“制度を知る者”には甘い
なぜこんなにズルく見える抜け道が許されているのか?
答えは皮肉ですが明確です:
「制度を作っている側の人間(財務官僚・上級国民)が使っているから。」
- 財務省官僚→国家出張日当
- 大企業役員→役員報酬/法人節税
- 経営者→分社スキーム/家族法人
つまり、自分たちの使っている抜け道は残す設計になっている。
これが本書の語る「日本社会の階級ロジック」の正体です。
まとめ:制度の“被害者”で終わるか、“使い手”になるか
「制度は平等」ではありません。
むしろ、制度は知っている人にだけ利益をもたらす設計になっています。
| 損する人 | 得する人 |
|---|---|
| 給与天引きのサラリーマン | マイクロ法人を作った人 |
| 制度を知らずに従う人 | 制度を読み解き、使う人 |
| 頑張っても手取りが増えない人 | 経費を増やして課税を減らす人 |
4.マイクロ法人を使った「お金が残る仕組み」の実践法
──制度に勝つには、“制度を使う側”に回るしかない──
そもそもマイクロ法人とは何か?
マイクロ法人とは、「個人が節税・社会保険料の最適化のために設立する超小規模法人」です。
- 自分自身が代表取締役になる
- 従業員はいなくてもOK(配偶者や子供を役員にするのも可)
- 報酬や経費、収支の流れを“自分で設計できるのが最大の強み
つまり、会社を持つことで「自分の働き方やお金の流れを自分でコントロール」できるようになります。
マイクロ法人の“節税・節保険メソッド”の全貌
ここでは、具体的な設計手法を3つのステップで解説します。
ステップ①:役員報酬を意図的に低くする
▼なぜ役員報酬を下げるのか?
- 社会保険(厚生年金・健康保険)の加入基準は「報酬額」で決まる
- 報酬を96万円未満にすると、所得税・住民税・社会保険のすべてが非課税ゾーンに収まる
- 国民健康保険に切り替えることで保険料も最小化可能(所得連動のため)
▼つまり…
役員報酬を減らせば、個人の課税も保険料負担も“極小”に抑えられる。
ステップ②:法人にお金を残す&使う
報酬を抑えたことで法人側に利益が残るようになります。
ここで重要なのが、「法人で使えば経費になる」という点です。
▼法人の“経費にできる支出”の例:
| 支出項目 | 経費になる理由例 |
|---|---|
| 自宅の一部家賃 | オフィス利用割合で按分できる |
| 通信費・電気代 | 仕事用PCやスマホの通信・電源使用 |
| 書籍・新聞・講座 | 情報収集・自己研鑽は業務上必要 |
| 車両・ガソリン代 | 移動・営業活動に使用していれば可 |
| PC・スマホ購入費 | 仕事道具として全額経費化可能 |
▼さらに注目すべきは…
法人に残った利益は「法人税」だけがかかる
→ 個人と違って経費でガンガン落とせる上に税率も18.5%と低い
ステップ③:家族を役員にして所得分散
これは合法的な“家族ぐるみ節税”の最強メソッドです。
▼例:専業主婦の妻を副社長に任命し、報酬を96万円に設定
- 年収96万円以下なら、所得税・住民税はゼロ
- 配偶者控除も活用できる
- その96万円は法人側では経費として差し引ける(税負担減)
- 実質、手取りと経費を“同時に稼ぐ”魔法のような手法
さらに、子供が大学生でアルバイトしている場合も、マイクロ法人に役員として所属させ、報酬を支払うことで同様の所得分散が可能になります。
出張日当制度:合法でお金が“湧き出す”抜け道
法人ならではの「出張日当規定」も節税界隈では有名なスキームです。
▼ポイント:
- 出張のたびに、定額日当(例:1日5,000円〜)を非課税で支給できる
- 実費(交通費・宿泊費)に加えて、「かかったであろう費用」という名目で支給OK
- 領収書不要・課税されない → 法人側で経費にできる
- 役員にも日当は支給できる(=自分に対しても合法的に)
▼極端な例:
- 夫婦で京都へ旅行 → “取締役会議”と名目で出張に設定
- 1人日当1万円 × 2名 × 2日間 = 4万円を非課税支給&経費化
国家公務員が出張時に日当をもらっている制度と同じロジックです。
なぜ税務署は“見逃している”のか?
「これって本当に合法なの?いつか潰されるのでは?」
と心配する人もいるかもしれませんが、答えはこうです:
財務省や官僚、大企業の役員もまったく同じ手法を使っているから。
- 出張日当:官僚にも日当が支給されている
- 法人税優遇:大企業・政治家が使っている節税策
- 家族登用:中小企業の常套手段
つまり「上級国民の特権」として制度の中に意図的に残されている抜け道なのです。
そして、それを一般人が使っても合法である限り、税務署は口出しできないというわけです。
補足:青色申告の自営業とどう違う?
青色申告も「経費が使える」「所得分散できる」という点で優秀ですが、以下の点でマイクロ法人に劣ります:
| 項目 | 青色申告(自営業) | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 所得区分 | 個人所得(最大45%課税) | 法人所得(最大18.5%) |
| 家族への給料 | 制限あり/手続き複雑 | 役員報酬として経費化可 |
| 社会保険義務 | 任意加入 | 報酬調整で加入免除可能 |
| 日当制度 | なし | 出張日当規定の適用可 |
つまり、税金・保険・制度面すべてにおいて、マイクロ法人の方が圧倒的に有利なのです。
実行時の注意点・落とし穴
- 設立時の費用(合同会社で約6〜10万円)
- 毎年の法人住民税(赤字でも最低7万円前後かかる)
- 適当な経費計上は税務調査の対象になりやすい(領収書管理は必須)
- 税理士との連携はある程度必要(顧問なしでも可能だが不安なら月1万円前後)
とはいえ、年収300万円以上ある人ならデメリットを軽く上回ると本書では明言されています。
まとめ:「手取りが増えない」悩みを根本から解決する唯一の方法
「給料を上げる」のは難しい。でも、「取られるお金を減らす」のは自分で選べる。
これこそが、本書が最も伝えたい「日本の制度で“勝つ”ための知恵」です。
| 項目 | サラリーマン | マイクロ法人活用 |
|---|---|---|
| 所得税率 | 最大45% | 法人税18.5%+経費で圧縮可 |
| 社会保険料 | 自動で最大課税 | 役員報酬調整で最小化可能 |
| 経費 | 制限あり | 自由度高く合法的に処理可 |
| 家族報酬 | 制限・控除上限あり | 経費で全額処理可能 |
| 日当制度 | なし | あり(税務署公認) |
前半まとめ
世の中会社員では社会保険料や税金を沢山払っているので、賢く生きる為にマイクロ法人を立てようというのが本書の主張でした
後半ではマイクロ法人を持つとどれだけ得をするかにについて解説しているので是非そちらも見てください
マイクロ法人についてはこちらの動画でも解説されています
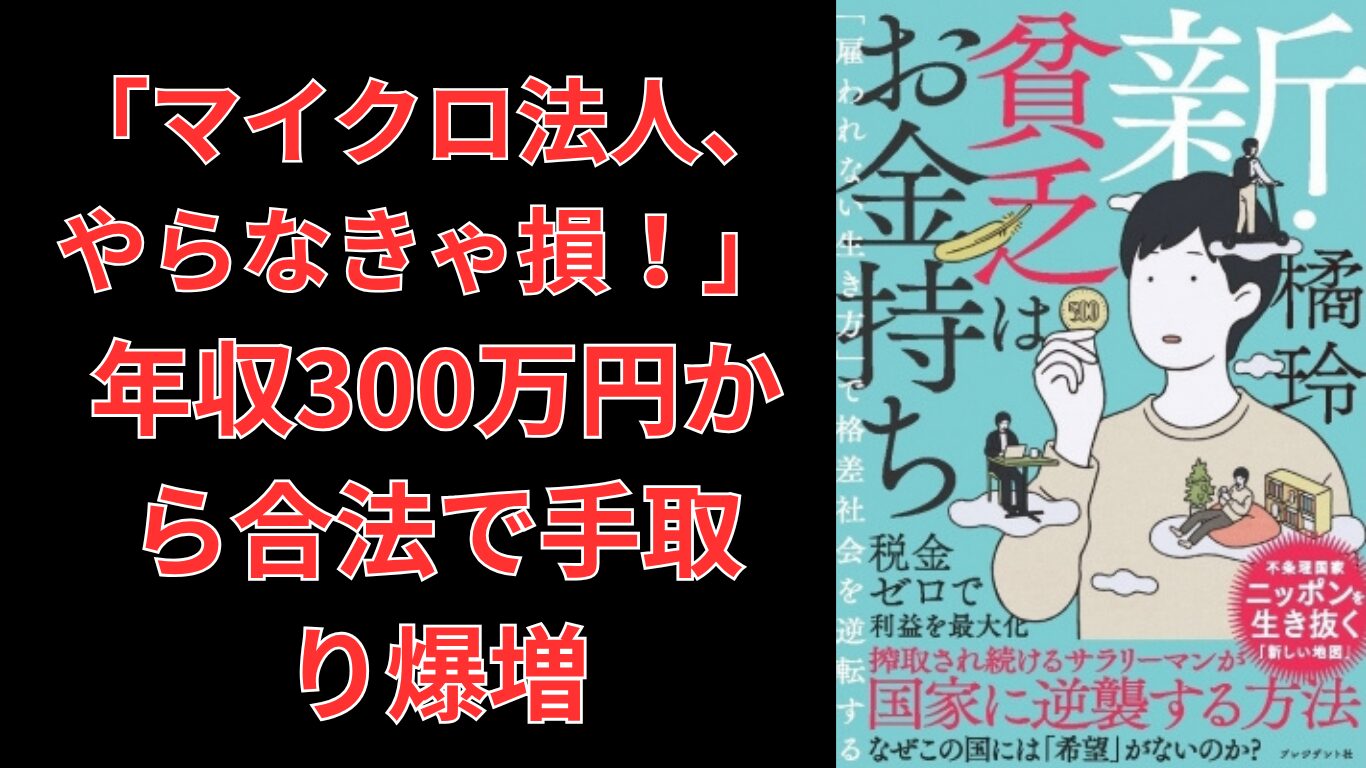


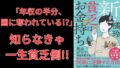
コメント